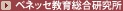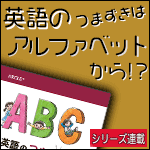研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
「研究ノート」は、ARCLEの研究理事・研究員が注目する自由なテーマを執筆するコーナーです。今回は、慶應義塾大学・田中茂範先生です。
概念を定義することの大切さ
慶應義塾大学 田中茂範先生
ぼくは、自分のことを英語教育に軸足を置く応用言語学者だと思っている。しかし、大学では「英語教育」を実践したり教えたりする機会はあまりなく、「言語コミュニケーション論」「認知意味論」「意味空間分析」「語彙意味論」といった講座を学期ごとに教えている。すると、言語学一般で使われる用語で気になるものが出てくる。
先日、意味空間分析の講義で話題になったのが「テクスト(text)」と「ディスコース(discourse)」の違いである。それぞれは、text linguistics だとかdiscourse analysisと呼ばれ、互いに関連した領域とされる。しかし、「テクスト」と「ディスコース」はどういう関係にあるのか。この問いに対して明快な解答は言語学分野でも示されていない。
この2つの用語の違いについて考えていくうちに、概念の定義の問題が本質的であるということに気がついた。そこで、このコラムでは、ぼくが大学生・大学院生に「テクスト」と「ディスコース」の違いについてどう説明しているのかを示し、さらに、概念の定義について講義した内容を簡単に「再録」してみたい。
テクストとディスコースの違い
まず、「言語」というものをどう捉えるか。これは、言語観にかかわる問題であり、言語研究の出発点とするべき前提である。これまで、言語の捉え方として、ラング(構造)としての言語とパロール(発話)としての言語が峻別されてきた。実は、この2つの言語観に対して、第三の捉え方がある。それは、コンピテンスとしての言語であり、Noam Chomskyが明示的に示した言語観である。コンピテンスとしての言語は言語主体を立てるところに特色がある。コンピテンスとは何であるかを直接問う言語学派の代表が生成言語学である。しかし、その生成言語学は数ある可能性の1つであり、コンピテンスをどう捉えるかは原理的に一枚岩ではない(ラングとしての言語とパロールとしての言語についてはこれまで言語学の通説であった。しかし、意外と、「コンピテンスとしての言語」という捉え方が他の2つと並置して語られたことは言語学でもあまりない)。
さて、「テクスト」と「ディスコース」の関係について説明してみよう。まず、(主体の言語)コンピテンスにより、テクストが生成される。このテクストはコトバの集積であり、コトバとしての産物である。テクストそのものを研究する流派がテクスト言語学と呼ばれるものであり、その主たる狙いはテクストの構造分析(文体と形態の研究)である。
しかし、テクストそれ自体はそれが紡ぎ出されたコンテクストからは独立している。そこで、テクストを言語行為の場であるコンテクストに戻すと、そこにディスコースが生まれる。これが、ぼくの見解である。ディスコースは時間と空間を伴う場であり、そこには出来事(event)があり、参加者(participants)がいる。ディスコースをジャンル・レジスターで分類すると、政治ディスコース、日常ディスコース、理論ディスコース、報道ディスコースなどに分かれる。
例えば、米国大統領の就任演説を考えてみよう。演説そのものはテクストとして記録されている。テクストそれ自体を取り出して、構造分析を行い、文体的な特性やフォルム上の特徴を明らかにすることもできるだろう。それと同時に、分析者は、テクストをディスコースに戻すという作業(試み)も可能である。すると、時代状況が考慮され、テクストのメッセージ性がクローズアップされると同時に、テクストを表現する大統領の戦略性に関心が向かうだろう。大統領のスピーチには戦略的な意図が込められているのである(大統領候補者になるためのスピーチ、大統領選出者〔president-elect〕としてのスピーチは大統領としてのスピーチとは目的性が異なる)。
さて、このように、コンピテンスとしての言語観に立脚し、主体が生成するテクスト、それにテクストが生成されるディスコースの場ということを考慮すると、「テクスト」と「ディスコース」というこれまで境界が不明瞭だった概念が、理論的枠組みの中で差異化されることになる。これが、概略、「テクストとディスコース」についてのぼくの最近の考え方である。ちなみに、「社会言語学」とは何か。ぼくが考える社会言語学は、使用者の属性と言語使用との関係に着眼するものである。この考え方はJ. Fishman というよりも、W. Labovのものに近い。ディスコースがタイプ化された類型概念であるのに対して、社会言語学的観点は、現象する出来事そのものに注目する。すなわち、社会言語学はタイプ(type)ではなくトークン(token)の研究を行うところにその真骨頂がある、というのがぼくの見解だ(もちろん、Fishmanのように社会というマクロ・コンテックスの中での言語使用ということを捉えれば、社会言語学は、ディスコースという概念を遥かに超えた領野となる。言語政策なども社会言語学の研究課題となるのである)。
言語を扱う研究者としては、「意味とは何か」「文法とは何か」「指示行為とは何か」等々、研究を進める上では、取り扱う概念の操作定義(operational definition)を行う必要がある。言語学などの教科書を読んでも納得の行く定義がないことが多い。そこで、自分で考え、判断し、自分なりの定義を行うということが、オリジナルな研究を行うためには必要なのである。しかし、定義を行うということは容易なことではない。そこで、「定義」そのものについて考えてみよう(といった感じで講義は進む)。
定義と例示
定義とは、概念同士の差異化を行うことである。がしかし、定義は、「AはBである」という表現形式を用いてしか行い得ない言語行為であり、表現の有意味性を確保する条件として「A≠B」の意味的差異が前提となるため、結局、「AはBではない」という裏返しの論理がはたらくことになる。この意味的差異は、一方では、Aを語り尽くすことができないということを、他方では、その限界性ゆえに、Aの言説の新たな可能性が絶えず開かれている、ということを同時に示している。
いずれにせよ、「AはBである」という表現形式を用いて用語の記述を行うわけだが、概念間の差異を示す定義だけでは、Aがどういうものであるかを示すことはできない。そこで、定義に加えて、用語の説明を行うことが必要となる。
定義が「Aとは何であるか」を規定する行為であるのに対して、説明は「Aはどういうものか」を明らかにする行為である。すなわち、定義は概念の差異化のために必要な行為であり、「何であるか」を明かせば、その役割は終わる。一方、説明は、「何であるか」ではなく、「どういうものであるのか」を明らかにするものであり、それを通して、用語(=概念)の意義が相手に了解されるのだろうと思う。少なくとも、辞典の編纂者や研究者は「定義」と「説明」とを自覚的に峻別して、用語の内容記述をしていかなければならない。
通例、定義というものは、それを厳密に行おうとすればそれだけ、わかりにくくなるものである。例えば、ある国語辞典では「リンゴ」を<バラ科の落葉高木、またはその果実>と定義している。このままでは、かえってわかりにくくなる。そこで、説明がどうしても必要となるわけだが、説明の善し悪しは、相手が何を辞典に求めているかに依存する。これは理論研究についてもいえる。
説明は例示を主として行うが、それは定義あっての説明であって、定義のない説明では、不十分である。例えば、「社会正義」の定義として、「『社会正義』とは公正な手続きを踏むことである」と記述したとしよう。このままでは、すっきりとは理解されない。そこで、それはどういうことかを説明するために、「二人の少年がいて、ケーキがある。母親は、ケーキの取り合いを避けるため、少年Aにケーキを切らせ、少年Bに選ばせるという手順を提案した」といった事例を挙げるかもしれない。しかし、例だけ示され、これが社会正義だ、といわれても、合点がいかない。定義上、公正な手続きとしての正義論が示されて、はじめて、説明が意味を成すのである(と結論づけながら、講義を締めくくるにあたり、メッセージを残す)。
このように、定義のない説明は不十分である、例証(説明)のない定義は不十分である。このことを、研究者はしっかり押さえておく必要があるように思う(これは、ぼくの気づきでもある。この気づきを大切にしながら、応用言語学者としてオリジナルな研究とその応用実践を進めていきたいと思っている)。