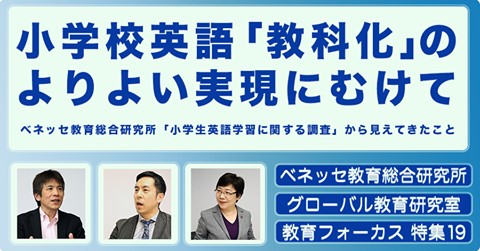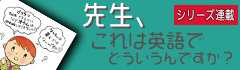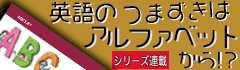研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
【新企画リレーコラム】言語能力育成を考える
≫このリレーコラムのその他の記事はこちら
第3回 「CEFRから読み解くタスクベースの言語能力発達」前編
東海大学 長沼 君主
CEFRの次期学習指導要領における影響
次期学習指導要領に向けての改革の流れの中、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のベンチマークとしての役割が大きくなっている。平成27年度「英語教育改善のための英語力調査事業(高等学校)報告書」(※1)では、高校3年生時で、受容技能がA1上位からA2下位レベルに分布が集中しているのに対して、産出技能ではA1の下位レベルにかけての裾野の割合が高い結果であり、技能間のバランスが課題とされている。ただし、平成26年度の同調査結果と比較すると、A1レベルの比率には改善が見られており、次期学習指導要領では、中学校においてA1からA2レベル、高校ではA2からB1レベルの達成が目指されている。
また、大学入試においても外部試験結果の活用が推奨され、大学入試センターによって認定された各資格・検定試験とCEFRとの対照表(※2)が公開されるなど、試験結果を国際的な基準に照らし合わせた際の目安として用いられている。間接的な影響としては、CEFRのフレームワークに準じて、これまでの4技能に代わり、話すことを「発表」と「やり取り」に分けた5領域で能力発達を考えることになる点も大きい。
さらに、CEFRの行動中心アプローチ(action-oriented approach)の考えを取り入れた「CAN-DOリスト形式」による学習到達目標の設定も促進されており、平成28年度「英語教育実施状況調査」(※3)では、設定率が高校で88.1%、中学校で75.2%と、平成25年度調査でそれぞれ33.9%と17.4%であったことを考えると、急速に広まってきていることが伺える。
しかしながら、学習到達目標の達成状況の把握に関しては、高校で41.6%、中学で34.2%とまだこれからの状況であり、実施をすでに行っている学校においても、どのように把握しているか、さらには、評価から逆向きに言語活動を設計し、学習と評価が一体化しているかも、今後問われるであろう。外部試験の活用が行われる中、CEFRのレベルだけが独り歩きしてしまうことなく、それぞれの個人が個々の言語活動で何ができるようになっているのかのプロファイルを描き(※4)、各言語活動での能力発達段階を踏まえた言語能力育成が行われる必要があるだろう。
CEFR/CEFR-Jの参照枠と能力記述尺度から見えてくるもの
CEFRのフレームワークを参照する際には、それぞれのレベルでできるようになることの指標として漠然と眺めるだけでなく、どのような言語活動が代表的な活動として記述されているのかにも着目することで、大きく言語発達とバランスをとらえることができる。
日本の文脈に合わせて調整されたCEFR-Jでは(※5)、A1を下位の3つのレベル、A2を2つのレベルに細分化するなど、よりきめ細やかに能力発達が記述されている。例えば、読むことであれば、A1.2で簡単なポスターや招待状など、A2.2で旅行ガイドブックやレシピなどの「媒体」から必要な情報を得ることができるといった「課題(タスク)」をこなすことができるようになる。一方で、物語に関する記述はA1.3、A2.1、B1.2で見られるなど、一つの技能を取り上げても多種多様な言語活動に関する能力記述が集まって構成されていることが分かる。実際の能力記述文は課題がどのような「条件」のもとで達成できるかとともに記述されており、条件を変えることで上下のレベルに調整しながら課題として扱うことができるだろう。
CEFRには全体の見通しを立てるうえで役に立つこうした自己評価のためのフレームワーク(self-assessment grid)だけでなく(※6)、個々の言語活動(タスク)の発達段階を記述した能力記述尺度(illustrative scales)(※7)も存在し、ある特定のタスクがどのようにできるようになっていくのか、フレームワークでは欠けている記述を補うことができる。例えば、上記に挙げたような情報を検索するといった「目的を持った読み(reading for orientation)」の尺度で、より上位のレベルでどのようなことができるようになるのかを見てみると、B1では複数の別の場所から情報を集めることができると記述されている。逆により専門的な内容に関する読みの力に関して、CEFR-JではB1.1で新聞や雑誌の記事の要点を理解する力、B1.2で図表と関連づけながら参考資料を読む力の記述があるのに対して、「情報や議論のための読み(reading for information argument)」の尺度では、下位の力としてA2でイベントのチラシや手紙、短い新聞記事などの情報を特定する力が記述されているなど、タスクごとの能力発達のつながりが見えやすい。
CEFRのフレームワークを見るとBICS(基本的伝達能力)からCALP(認知・学術的言語能力)へと能力発達をしていくように見えがちであるが、それは必ずしも下位のレベルでCALP的な能力は扱えず、上位のレベルでBICS的な能力は求められないということではない(※8)。能力をレベルとして一律に規範的(prescriptive)にとらえるのではなく、特定のタスクをどのレベルでこなせるようになっているかのプロファイルとして、目の前の能力を記述的に(descriptive)にとらえる必要性もここにあり、帰国子女など、BICS的能力が先行し、CALP的能力が追い付いていない、または逆に、学校教育の中でCALP的な能力は身についているが、第二言語習得環境であれば日常的に身につけていることが想定されるBICS的な能力に欠けるといったこともある。
CEFRのもう一つの重要な考え方に部分的な能力(partial competence)の肯定があり(※9)、母語話者モデルによるのではない能力発達観がある。タスクが「できるようになりつつある」過程である下位の能力を、不完全な能力としてみなすのではなく部分的な能力ととらえ、個に応じた発達や足場がけを肯定的な証拠ととらえることが、課題遂行への自己効力(できる感)を高め、自律的学習を促進するであろう。足場がないとできないのではなく、足場があればこれくらいできるといった価値観の転換が教師にも学習者にも求められる。
CEFRの能力記述尺度には、何をどの程度できるか(quantity)を記述したコミュニケーション活動の尺度だけでなく、どうできるか(quality)を記述した語彙や文法、音声面、さらには社会言語能力や語用論的能力等の言語的要素(コンピテンス)の発達に関する尺度もある。ある特定の課題遂行において正確さと流暢さは同時に求められるのかなど、課題に応じて要求される適切な言語面の能力発達やさらに上のレベルでの課題の到達を考える際に参考となる(※10)。さらには推測や自己モニタリングと修正などのコミュニケーション方略に関する尺度もあり、コミュニケーション活動を支える足場を考える上で方略能力の発達も重要となる。
前編はここまでです。後編「CEFRの補遺版(Companion Volume)から見えてくるもの」に続きます。
後編はこちらから。
1) 平成27年度「英語教育改善のための英語力調査事業(高等学校)報告書」
2) 各資格・検定試験とCEFRとの対照表
3) 平成28年度「英語教育実施状況調査」
4) North(2014)では、"Profiling not leveling"とし、CEFRのレベルだけで能力をとらえるのではなく、個々の能力記述文に基づいたプロファイルを描く必要性を指摘している。
5) CEFR-J。詳しくは、投野(2013)を参照のこと。
6) Relating Language Examinations to the CEFR: A Manualには、産出技能と受容技能のそれぞれでA2+などのプラスレベルも含めた各レベルの顕著な特徴がまとめられている。
7) Structured Overview of all CEFR scales。各技能全体尺度も含めて53の尺度がある。
8) Little (2011)でもBICSからCALPへの移行における下位レベルのCALP的能力記述の必要性を示唆している。
9) Heyworth(2004)でも部分的能力の重要性が指摘されている。
10) 産出技能に関しては、評価ルーブリック(Oral and Written Assessment Criteria Grid)の形でまとめられている。注6のA Manualを参照のこと。
参考文献
Heyworth, F. (2004). Why the CEF is important. In K. Morrow (Ed.). Insights from the Common European Framework. Oxford University Press (pp. 12-21).
Little D. (2011). The Common European Framework of Reference for Languages: A research agenda. Language Teaching, 44(3), 381-393.
North, B. (2014). The CEFR in Practice (English Profile Studies 4). Cambridge University Press.
投野由紀夫[編](2013).『CAN-DOリスト作成・活用 英語到達指標CEFR-Jガイドブック』 大修館書店.
【リレーコラム一覧】