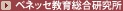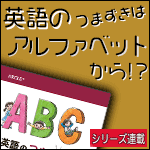研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
【新企画リレーコラム】言語能力育成を考える
第1回 マイ・イングリッシュの育成
慶應義塾大学 田中茂範
はじめに
英語教師であればだれでもよく耳にする「英語が使える日本人の育成」というコトバの裏には、「日本人は英語が使えない」ということがある。英語が使えるようになるには、英語を使うしかない。これは紛れもない事実である。しかし、生徒がいざ英語を使おうとすると、それを阻む要因が存在する。その要因はいくつか考えられるが、ここでは、筆者が特に重要だと考える「心理的要因」と「環境的要因」について所見を述べてみたい。
心理的要因
中高時代の英語といえば、「教科書の中の英語」、「問題集の英語」、そして「試験(入試を含む)の英語」であったと漏らす大学生が多い。そうした英語教育においては、英語の問題が解ける人が「英語ができる人」となる。しかし、「英語を使う力をつける」ということからみれば、これは「歪められた英語教育」の在り方である。というのは、ほとんどの大学生が「英語は勉強したが、使えない」と感じているからである。
英語は使うことによってしか使えるようにならない。ということは、本来の英語教育においては、「誤りをすることを恐れるな」、というよりむしろ「どんどん誤りを犯そう、そして英語力を伸ばそう」という発想を持たなければならない。Don't be afraid of making mistakes. という言い方には、「誤りをおかす」ことは怖いことだという前提を読み取ることができる。そこで、Make more mistakes and make progress.という発想の実践が肝心なこととなる。
しかし、「『問題が解けること』イコール『英語ができること』」と捉える英語教育では、「誤り」は減点の対象になる。そして、学ぶことが「永遠」に続く学習過程においては、いつも「足りない」という気持ち(a sense of inadequacy)が付きまとい、英語を話すということに対して抑制がはたらいてしまう。「足りない」という気持ちは、英語を実践的に使うことに際してマイナスに作用する心理的要因である。
マイナスの心理的要因はそれだけではない。英語は所詮「外国語」である。英語でa foreign languageというようにforeign(馴染みのないもの)なのである。それは、自我にとっては「異物」である。自我は言語発達とともに発達する。つまり、個人の中で言語は自分らしさと密接に結び付いている。人には、それぞれ「その人なりの語り口」というものがあり、母語であれば、自分らしさを表現することができる。だが、英語を使う自分は、「自分らしくない」と感じる人が多いようである。
英語はできないよりできたほうが良いという思いがある一方で、いざ英語を使おうとすると、不自然で、自分らしくないという思いが強くなる。そして、こうありたいという「理想的な自己(ideal self)」と「実際に英語を使っている自己(performing self)」の大きなギャップに、戸惑いや違和感や不快感を覚える。そういう状況で、英語を話そうという気持ちにはなかなかならない。英語を話そうとする試みを「恥をかきたくない」といった自我の防衛本能がくじくのだといってもよい。
かくして、英語を使うことに対して二重の心理的負荷(「足りない」と「自分らしくない」)を抱えることになる。では、どうすればよいか。これは容易な問題ではないが、まず、「英語はだれでもやればできる」という信念を教師も生徒も共有することが必須である。学校時代は英語が苦手だったが、仕事の関係で必死に学び、今では英語で仕事をしているという人がたくさんいることを考えてみればよい。外国人力士やテレビなどで活躍する外国人の日本語を考えてみればよい。筆者がよく引き合いに出すのは、還暦をすぎて第二の活躍の場を国際協力に移すJICA(国際協力機構)のシニアボランティアの事例である。シニアボランティアの中には、例えばスリランカで仕事をするためシンハラ語を60歳前後で学び、かなりのレベル(その言語を運用することができるレベル)まで高めた人も少なくない。
英語はだれでもやればできる。しかし、それ(その信念)だけでは十分ではない。「自分自身の英語を構築する覚悟」を生徒一人一人が持つことが肝心である。教科書や問題集の中の英語(自分の外にある英語)ではなく、自分が所有者となる、自分の中に息づく英語である。筆者は、そういう英語を"my English"と呼んでいる。my Englishとは、個人一人一人の英語力(英語を理解したり表現を紡ぎ出す力)のことをいう。英語を母語として使っている人はだれでも、自分の英語(my English)を持っている。我々も、英語学習を自分事として捉え、一人一人のmy Englishを構築するという覚悟を持つことが必要である。
そして、自らのmy Englishを表現者として使うことを楽しむことである。それは一人一人にとって新しい言語能力であり、その新しい言語能力を駆使して表現することを、たとえ「ぎこちなさ」があっても、楽しむことである。その都度のmy Englishで勝負することである。使うことによってmy Englishは機能性を高め、次第に自分らしい英語が発達してくるはずである。教師の役割は、生徒が自らmy Englishの育成を行う過程を支援することである。
環境的要因
学習者が「my Englishの構築を行う」という強い覚悟を持ったとしても、それを実行に移し、学習効果を生むようにするには、環境的要因を考慮する必要がある。ここでいう環境的要因は、次の3つの条件のことを指す。それは、①language exposure(LE)の質量の条件、②language use(LU)の質量の条件、そして③urgent need(UN)の存在の条件である。LEはインプットの問題、LUはアウトプットの問題である。my Englishを育てるには、たくさんのインプットに触れることが必要だし、たくさん英語を使うことが必要である。英語が日常的に使われる環境であれば、この2つの条件はたいてい満たされることになる。英語に触れ、英語を使うという必要性(すなわち、UN)が存在するからである。この3つの条件が満たされたとき、my Englishが創発する可能性の高い環境が生まれる。
日本の学校英語教育の中でこの3条件が満たされるような環境設計が行われてきたかといえば、疑問がある。がしかし、日本にいながらにしてどうやって3条件をクリアするか、これこそが「使える英語」を目指す英語教育が取り組むべき本質的問題である。
英語に触れる量の条件については多読・多聴の実践で何とかなるかもしれない。しかし、「英語のシャワー」を浴びるだけでは十分ではない。また、生徒中心の授業の中で、生徒の英語での発言機会も増えている。しかし、やみくもにたくさんの英語に触れ、たくさんの英語をしゃべるというだけでは、十分ではない。生活言語として英語が使われる状況では、圧倒的な量が質も保証する。自然(holistic)な形で英語を学ぶ中で、必要な英語に触れ、必要な英語を話すという選択が行われるからである。しかし、日本の教室で英語を学ぶには、LEとLUの質の問題をしっかり考え、教育支援ができるような工夫が必要である。教室は、自然な形で英語に触れ、英語を使うという場にはなりにくい。UN(差し迫った必要性)がないからである。しかし、質の問題がクリアされれば、UNの問題もある程度は自然と解決されると筆者は考える。
これまで質の問題は本質的でありながら、それを議論する枠組みが示されてこなかったように思う。問題の在処が示されなければ、問題解決の糸口は見えてこない。結論をいうなら、生徒にとってmeaningfulで、authenticで、そしてpersonalな教材の提示と活動を行わせることに尽きる。これが筆者の考えである。meaningfulとは、生徒にとって理解可能であると同時に、おもしろいと思い、そしてやる価値があると実感することができるということである。authenticとは生徒が本物と感じる(リアリティを感じる)ということであり、そしてpersonalとは生徒が自分事として、すなわち、自分の英語(my English)を構築するのに役立つと感じることである。meaningfulで、authenticで、personalな活動を提供すれば、教室は英語を自然な形で使う場に変わる。そして、そういう場づくりが、英語を使うことに対する必要性を生み出すのである。
おわりに
生徒がmy Englishを構築することができるように教育的支援を行うこと、これが英語教育の本務である。ここでいう教育的支援を行うには、language exposureの質量、language useの質量、そしてurgent needの存在という3つの条件を満たすような場づくり(環境づくり)が必要となる。
my Englishを構築するという課題は生徒の自律性に拠ることは言をまたないが、my English構築の場を提供するのは教室である。教室という場がLEの質量、LUの質量、そしてUNの存在という条件を満たすことができれば、その中で一人一人のmy Englishが育つ可能性が生まれる。筆者の提案は、生徒にとってmeaningfulで、authenticで、personalな教育活動を多くすれば、自然と、ここでいう3つの条件は満たされる、というものである。
そして、今回は触れないが、meaningfulで、authenticで、personalな場づくりに貢献するのは、ICT(コンピューターを中心とする情報通信技術とその技術を使ったデバイスの総称)であることを付け加えておきたい。
【リレーコラム一覧】