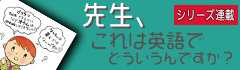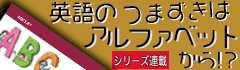�����m�[�g�E������|�[�g�ꗗ
- 2024�N�x
- 2023�N�x
- 2022�N�x
- 2021�N�x
- 2020�N�x
- 2019�N�x
- 2018�N�x
- 2017�N�x
- 2016�N�x
- 2015�N�x
- 2014�N�x
- 2013�N�x
- 2012�N�x
- 2011�N�x
- 2010�N�x
- 2009�N�x
- 2008�N�x
�y�V��惊���[�R�����z����\�͈琬���l����
≫���̃����[�R�����̂��̑��̋L����������
��3��@�uCEFR����ǂ݉����^�X�N�x�[�X�̌���\�͔��B�v���
���C��w�@�����@�N��
�O�҂́������w�K�w���v�̂ɂ�����CEFR�̉e�����A
��CEFR/CEFR-J�̎Q�Ƙg�Ɣ\�͋L�q�ړx���猩���Ă�����́��ɑ����A��҂ƂȂ�܂��B�i�O�҂���ǂ܂����́A�������ցB�j
CEFR�̕��ŁiCompanion Volume�j���猩���Ă�����̇@�F���[�h�ƃ}�N���@�\
�@���ꊈ����\�͂��ƂɊe���x���̋L�q�����ړx������illustrative scales�́A2018�N2���Ɍ��J���ꂽCEFR�̕��łƌ�����The CEFR Companion Volume with New Descriptors�iCEFR/CV�j��11�ɂ����đ啝�Ȍ������Ɗg�[������Ă���APre-A1���x���̋L�q�̒lj���C���x���̋L�q�̏C��������A�V�K��Mediation�i�}��j�̗̈�̎ړx���J�������Ȃǂ��Ă���B�ʂ̃^�X�N���̎ړx�Ɋ�Â����v���t�@�C�����d�������p����������������������f����B
�@�t���[�����[�N���]����5�Z�\�i�̈�j�̕���������A�R�~���j�P�[�V�������[�h�Ɋ�Â�Reception�AProduction�AInteraction�ɁA�V����Mediation���������������ɐ����ς��č��V���ꂽ�BCEFR���J�����ꂽ������Written Interaction�ւ̔F�m���Ⴉ�������Ƃ���Writing�ɂ܂Ƃ߂��ASpeaking�݂̂�Spoken Production��Spoken Interaction�ɕ�����ꂽ���A����̉����ł�Written and Online Interaction�̘g���݂������12�A��莞��̗v���ɉ������̂ƂȂ��Ă���B�����w�K�w���v�̂ł́A�b�����Ƃɂ�����CEFR�̓����ł����锭�\�Ƃ������Ă��邪�A����ɂ͏������Ƃɂ����Ă����l�̕��������烁�[����SNS�ł̂����ɂ����œ_�����ĂāA6�Z�\�i�̈�j����Z�\�o�����X��\�͔��B���Ƃ炦��K�v�����邾�낤��13�B
�@�R�~���j�P�[�V���������̕��ނɂ������ẮA���������R�~���j�P�[�V�������[�h����̐���ɉ����āA�}�N���@�\�Ƃ��āA�u�n���E�ΐl����g�p�iCreative, Interpersonal Language Use�j�v�A�u����E������g�p�iTransactional Language Use�j�v�A�u�]���E����������g�p�iEvaluative, Problem-solving Language Use�j�v�̓_����傫���J�e�S���[�������A�\�ɐ���������������������Ă���A�ړx����Ղ��ă^�X�N�Ԃ̃o�����X������Ă��������Ŏ����ƂȂ�ł��낤�B�Ⴆ�A��e�ireception�j�ɂ����Ēlj����ꂽ�u�y���݂̂��߂̓ǂ݁iReading as a leisure activity�j�v�͑n���E�ΐl����g�p�ɂ����邪�A����܂ł̓ǂ݂̎ړx�ł͌����Ă�����14�B�܂��A�Y�o�iProduction�j�ʼn�������u�����������b�F���iSustained monologue: Giving information�j�v�́A�]���̎����������b�Ɋւ���Q�̎ړx�́u�o���`�ʁiDescribing experience�j�Ɓu�ӌ��q�iPresenting a case�j�v���ΐl�E�n���ƕ]���E�������̌���g�p�ł��������Ƃ���A����E���̃}�N���@�\������Ēlj����ꂽ���Ƃ�������B
CEFR�̕��ŁiCompanion Volume�j���猩���Ă�����̇A�F�}��̏d�v��
�@����̉����̍ł��傫�ȕύX�ł���Mediation�́ACEFR�ł����y�͂���Ă������A�ʖ��|��ƂƂ炦��ꂪ���ł���A��̓I�Ȏړx���Ȃ������B�������A���ۂɂ͒ʖ��|���łȂ����ʓI�Ȕ}������Ӑ}����Ă���A�����łł͏�L��3�̃}�N���@�\�Ɋ�Â��āA�R�~���j�P�[�V�����̔}��Ɋւ���Mediating communication�i�n���E�ΐl����g�p�j�A�e�L�X�g�Ƃ̔}��Ɋւ���Mediating a text�i����E������g�p�j�A�ӌ��`���ɂ�����}��Ɋւ���Mediating concepts�i�]���E����������g�p�j�̘g����t���[�����[�N�ł��L�q������Ă�����15�B
�@�ʖ��|��͂��̂�����Mediating a text�Ɋ܂܂�邪�A����ȊO�ɂ��]���̎ړx�ł�Working with text�̃J�e�S���[�ŋZ�\�Ƃ͕ʘg�Ƃ���A���ʒu�Â��������܂��ł�����Processing text��Note-taking�̎ړx���܂܂��BProcessing text�́A��������A�ǂ肷�钆�ŁA�K�v�ȏ����o���āA�܂Ƃ߂���A�`���[�g�Ȃǂɐ������銈���ł���A�u�`���c�ȂǂŃ��������Note-taking�ƂƂ��ɋZ�\���܂����������I�����ƌ�����BMediating a text�ɂ́A�V����Relaying specific information �Ƃ������K�v�ȏ��̓`�B�����銈����}�\���ɋL���ꂽ�����������Explaining data�Ȃǂ̎ړx���݂����Ă���A5�̈悩���Ȍ��ꊈ�����L�q����ۂɁA�Ƃ�����Ɣ����Ă��܂������ȁA���ꊈ�����x���鉺�ʋZ�\�̔��B�����ׂ�������邤���Ŗ��ɗ��B
�@�����w�K�w���v�̂ł́A�m���E�Z�\�Ƃ���������I�Z�\�ilinguistic skills�j�ʂ����łȂ��A�ėp�I�Z�\�igeneric skills�j�Ƃ��Ă̎v�l�́E���f�́E�\���͂Ƃ����������E�\�͂̈琬���ڎw����A��̓I�őΘb�I�Ȋw�т���[���w�тւƂȂ��Ă������Ƃ���������Ă���BMediating concepts�ł́A�����I�Ȏv�l�̌`�����d�����Ă���A�O���[�v�ł̋������Ɋւ���Collaborating in a group�ƃO���[�v���[�N�̑��i�Ɋւ���Leading group work���āA���ꂼ��ŊW�ʂł̔}��irelational mediation�j�ł���Establishing conditions (for effective work)�ƔF�m�ʂł̔}��icognitive ;mediation�j�ł���Developing ideas�ɂ�����ړx��݂��Ă���B
�@�W�ʂł̔}��ɂ�Facilitating collaborative interaction with peers��Managing interaction��2�̎ړx������A�Θb�I�w�т��l���邤���ŁA�ǂ̂悤�ɑ���̔����������o���Θb�𑣐i���A�c�_�ɍv�����邩�A�܂��A���ꊈ���ɂ����āA�ǂ̂悤�ɂ��������Ȃ��狦����Ƃ��~���ɐi�߂邩���l����ۂ̎Q�l�ƂȂ�B����A�F�m�ʂł̔}��ɂ�Collaborating to construct meaning��Encouraging conceptual talk��2�̎ړx���܂܂�A�c�_�⊈���ł̑Θb�I�Ȋw�т̒��ŁA��������Ȃ���l�����`�����A�������Ă����ߒ����L�q����Ă���B�������������E�\�͂��ʂ̌��ꊈ���i�^�X�N�j�ɗ��Ƃ�����ŁA�ώ@�\�ȍs���Ƃ��ċL�q���Ă������ƂŁA���ׂ��Ȍ������̓I�Ȏv�l��Θb�̑��ꂪ�����\�ƂȂ�A���Ȍ��͂���݂Ȃ��猾��\�͂��琬���Ă��������ƂȂ邾�낤��16�B
11)�Q�ƃ����N The CEFR Companion Volume with New Descriptors�iCEFR/CV�j 2001�N�ɏo�ł��ꂽCEFR���̂̉����ł͂Ȃ��A�ړx��t��������`�ʼn������ꂽ�B
12)��7��Structured Overview��Self-assessment Grid�ɂ�Written Interaction�̘g��������Ă���A�Ȍ��ȋL�q��������B
13) �������ACEFR/CV�ł�6�Z�\�Ƃ����Ƃ炦���ł͂Ȃ��A��q�����悤�ɁAMediation��������4�̃��[�h�ɂ��܂��͌��ꊈ���ނ��Ă���B
14) �O�q�����悤��CEFR-J�ł͕���Ɋւ���L�q�������邪�ACEFR�ł͂Ȃ������B
15) �t���[�����[�N�ɂ�����L�ڏ��͈قȂ�B
16) ������グ�Ȃ�����Mediating communication�́A�ٕ����I�v�f���܂ރR�~���j�P�[�V�����ɂ�����}��ł���A�������Ԃł̌𗬂̑��i�⑼�҂Ƃ̐l�ԊW�ɔz�����������̑��i�Ɋւ���ړx�Ȃǂ��܂܂��B
�Q�l����
Heyworth, F. (2004). Why the CEF is important. In K. Morrow (Ed.). Insights from the Common European Framework. Oxford University Press (pp. 12-21).
Little D. (2011). The Common European Framework of Reference for Languages: A research agenda. Language Teaching, 44(3), 381-393.
North, B. (2014). The CEFR in Practice (English Profile Studies 4). Cambridge University Press.
����R�I�v[��](2013).�wCAN-DO���X�g�쐬�E���p �p�ꓞ�B�w�WCEFR-J�K�C�h�u�b�N�x ��C�ُ��X.
�{�L����ǂ��ɃI�X�X���L��
�����搶���o��I�w����t�H�[�J�X�@���W�P�X�x
���w�Z�p��u���ȉ��v�̂��悢�����Ɍ�����
�@�`�x�l�b�Z���瑍���������u���w���̉p��w�K�Ɋւ��钲���v���猩���Ă������Ɓ`
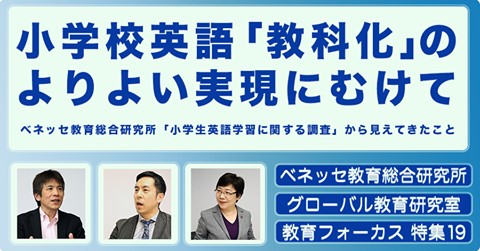
�y�����[�R�����ꗗ�z