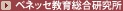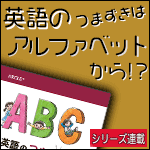研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
連載『言語の役割を考える』
第2回 意味知識と概念形成
田中茂範(慶應義塾大学名誉教授、PEN言語教育サービス)
はじめに
本連載の第1回目では、「コトバに意味がある」という意味の実在論的な見方から「コトバの意味はつくられる」という構成論的な見方にシフトした議論を行ってきた。意味づけの素材は、「記憶」である。例えば「学校」というコトバの意味がわかるということは、「学校」という文字に関する記憶をもっているからにほかならない。だとすると、「記憶」が「意味」ではないかという疑問がでてくる。
結論を先にいうと、記憶は、意味というより「意味知識」と呼ぶほうが適切である。そして、意味知識というものは、差異化・一般化・類型化を伴う概念形成の過程を通して得られるというのがここでの論点である。意味知識には、単語の意味知識や言語の操り方(文法)に関する知識だけでなく、行動の仕方に関する知識(行為のスクリプト)なども含まれる。本稿では、意味知識の形成についてみていきたい。
意味と意味知識の関係
まず重要なのは、「意味」と「意味知識」を区別することである。人は、例えば「犬」というコトバについて多くのことを知っている。それは意味知識であって、日常のやり取りにおける意味(意味づけられた意味)ではない。
人は、意味知識を利用しつつ、意味づけを行う。しかし、意味知識は、意味づけられる意味を決定することはない。Davidson(1978)は、日常会話を行う者は、何らかの意味理論を「先行理論(prior theory)」としてもっているが、それは会話場面に適用されたときに「意味」を確定するものではなく、必要に応じて改編される暫定的な「当座理論(passing theory)」として機能する、と述べている。先行理論、そして当座理論がここでいう「意味知識」である。すると、意味づけられる意味と意味知識は相互に媒介し合う関係に置かれることになる。意味知識を利用しながら意味づけを行うが、意味づけがまた意味知識の改編の契機になるということである。意味づけは、今・ここでの情況内で行われるため、潜勢態としての意味知識は、意味を決定し得ないのである。以下では、意味知識の形成についてみてみよう。
意味知識
コトバの意味知識とは、私たちがコトバについて知っていることであり、人がそのコトバについて説明するところのものである。そして、同時に、私たちは、「私がある語の意味について知っている内容は、同じ日本語を話す人であれば、ある程度は共通しているであろう」と考えている。だが問題は、個々人のそれぞれが抱く意味知識が共有しているという感覚をどのようにして獲得するか、である。意味知識を共有しているという感覚は、概念形成の原理に支えられている、というのがここでの論点である。
概念形成の原理
一般名に限っていうと、あるコトバ(W)の意味を知っているとは、「Wと非W」「いろいろなW」「WらしいW」について知っているということである。つまり、「差異化・一般化・類型化」の相互作用を通して概念は形成され、そのプロセスの中で意味知識の秩序化(概念形成化)が図られる(詳しくは深谷・田中 [1996]の第3章参照)。
例えば「犬」というコトバを使用するには、犬とそうでないものを差異化すること、いろいろな対象に対して「犬」というコトバを使用できること、犬らしい犬についての直観をもっていることが要請される。「犬らしい犬」の直観がなければ、「変わった犬」「おもしろい犬」「ふつうの犬」という記述が不可能になるはずである。また「リンゴ」のことを「赤い丸いリンゴ」といちいち表現しなくても、<赤い丸いリンゴ>が了解されるのは、「リンゴ」の典型的知識に<赤い>と<丸い>が含まれているからである。
概念形成のプロセスについて強調すべきは、差異化・一般化・類型化は絶えず相互に作用し合うということである。「らしさ」は類型化(典型的な共通特徴に注目して概念を形成する過程)の作用結果であるが、一般化が作用しなければ、通常、類型化も作動し得ない。一般化は言語の経済性の原理に支えられている。言語は有限であるが、個別事象は無限である。有限で無限に立ち向かうには一般化(いろいろな対象に同一語を当てる)という認知過程が必要である。
しかし、一般化が進めばコトバの意味上の差異をつけることが難しくなるが、差異化のはたらきを支えているのが類型化である。色のスペクトラムを考えてみるとよい。黄色と緑色のそれぞれの範囲が広がれば相互浸透する領域が生まれる。黄色か緑色かの識別が難しい状況もあるだろう。しかし、黄色らしい黄色と緑色らしい緑色においては、両者は容易に差異化できる。それだけではない。相互浸透領域にライム色という用語を充て、その類型化がはたらけば、二項対立的だった色から三項対立の関係(黄色・緑色・ライム色)が生まれる。類型化は差異化を支えると同時に、新たな差異を生み出すのである。
コトバ−−特に名詞・動詞などの内容語−−は、他のコトバと差異を図りつつさまざまな事態を描写するのに使用されるが、使用経験を通して典型的な使い方というものを身に付けていき、それが言語共同体内で共有され、言語慣習になる。これが意味知識に関する秩序性の形成原理である。経験が類似していれば自然と共同体内の人々の概念も類似したものになる。
ちなみに、社会学の術語に「ステレオタイプ」と呼ばれるものがあるが、それは特定の集団を過度に単純化し、描写する際に用いられる紋切り型の知識のことを指すというのが一般的理解である。しかし、ステレオタイプは、過剰一般化の産物というよりも、むしろ類型化の産物である、というほうが適切である。例えば、AがBに出会い、のちにAがCに出会い、Bについて話をするのに「Bはアメリカ人だ」と言ったとしよう。「アメリカ人」というコトバを使用することは、自動的に「非アメリカ人」との差異化を行うことである。しかし、それは複数の人を描写するのに用いられるコトバであり、他のアメリカ人との出会いが重なれば一般化が進むと同時に、「アメリカ人」という概念の典型的特徴が抽出され、それが次第に「アメリカ人らしさ」(類型化)に関する知識を形成する。勿論、この「アメリカ人らしさ」−−アメリカ人のステレオタイプ(認知心理学では「プロトタイプ」と呼ばれる)−−は個人的経験に依拠してつくられた概念であり、それが「アメリカ人」という集合概念を代表するものである保証はない。だからこそ、この「アメリカ人らしさ」の基準をアメリカ人と呼ばれる個人に当てはめようするとき、個人を特定の集団の型にはめることになり、過度の単純化が行われることになるのである。
この議論の自然な延長として、差異化・一般化・類型化は語レベルの概念形成に作用するだけでなく、行動にも作用するということが予想され、その結果として、スクリプトが形成される。行動のスクリプトとは「何々のしかた」に関する「手続き的知識(シナリオ)」であり、「議論のしかた」「蕎麦の食べ方」「講義のしかた」など無数のスクリプトを私たちはもっている。ここでも「変わった」とか「正当な」といった形容詞を使用できるように、差異化・一般化・類型化の作用の結果としての「典型的なやり方」というものがつくられ、それがある行動(言動を含む)の判断や評価の基準になる。この基準のことを知識レベルで「常識」と呼んでもよいし、行為レベルで「慣習」と呼んでもよい。
ここでの結論は、意味の共有感覚は、概念形成のしかた(一般化・差異化・類型化の相互作用)に支えられているということである。
【参考文献】
1) Davidson, D:A nice derangement of epitaphs. In Truth and interpretation: Perspectives on the philosophy of Donald Davidson, ed. By Lepore, E, 23-32, Basil Blackwell, Oxford (1986) .
2) 深谷昌弘・田中茂範:コトバの意味づけ論:日常言語の生の営み,紀伊国屋書店,東京(1996).