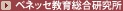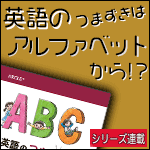研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
連載『言語の役割を考える』
第3回 用語の定義と説明
田中茂範(慶應義塾大学名誉教授、PEN言語教育サービス)
はじめに
コトバでコトバを説明する。これは言語の力である。この力がなければ、あらゆる種類の辞書・事典を作成することはできない。本稿では、コトバの説明のしかたに注目する。
まず、専門用語辞典を見てみよう。多種多様の辞典があるが、それが取り扱う項目のほとんどは名詞である。名詞はその性質上、指示作用があり、なんらかの対象を指す。といっても、名詞の中には知覚対象を指すものと観念対象を指すものがあり、知覚対象の場合、その対象が事物的に存在するという前提があり、その特徴―知覚的特徴、機能的特徴、行動的特徴など―を知覚することができる。しかし、「意思決定」や「共有信念」や「意味」のように、「それが何であるか」を記述することによってのみ、その指示対象(観念対象)を明らかにする場合がある。専門用語辞典などの被説明項は、ほとんどが観念対象を指す名詞である。
「がある」と「である」
同じ名詞でも知覚対象を指すものと、観念対象を指すものとでは、その意味編成のしかたにおいて決定的な違いがある。例えば、「リンゴ」という語は、知覚対象として存在する―「そこにxがある」という存在のしかたで存在する―対象を名指すことができ、その名指しという経験を通して、人は「これはリンゴである」「あれもリンゴである」という一般化(汎化)を行いつつ、「リンゴ」と「非リンゴ」の差異化を行う。そして、一般化と差異化と同期するかたちで、類型化の作用がはたらき、リンゴの概念が形成されていくということになる。すなわち、いろんなリンゴを経験し、そしてリンゴと非リンゴを差異化することを通して、いわゆる「リンゴらしさ」を特徴づける典型的特徴を内在化することでリンゴの概念を獲得する。
要は、事物名詞の場合、「がある」ということを前提に「である」を導くことができるため、比較的、意味の共有感覚を確保しやすいということである。共有感覚がある限り、いちいち定義したり、説明したりする必要がなく、「リンゴって何か」だとか「犬とは何か」といったことが話題にならないのである。
一方、専門用語辞典が取り扱う多くの名詞の場合には、「がある」と「である」の相互作用が起こらず、「AはBである」という表現形式を使ってその語についての定義をしたり、説明をしたりしなければならない。それらは、共通の知覚体験から創発される概念ではないがため、その捉え方に個人差が生まれ、議論や論争、時には紛争の対象になり得る。ここに専門用語の記述の難しさがあるように思う。
定義と説明
用語の記述には定義が不可欠である。定義は、「AはBである」という形式を使って行われるが、正確にいえば、「『A』とはBということを意味する」という意味合いを含む。例えば、「コトバの意味はコトバから構成される事態である」を「コトバの意味」についての定義文とみなせば、それは「『コトバの意味』とはコトバから構成される事態のことを意味する」ということにほかならない。すなわち、ここでは「コトバの意味」という語に自己言及しつつ、「(コトバの意味が)コトバから構成される事態であること」と定義する形になっている。
定義とは、概念同士の差異化を行うことである。がしかし、定義は、「AはBである」という表現形式を用いてしか行い得ない言語行為であり、表現の有意味性を確保する条件として「A≠B」の意味的差異が前提となるため、結局、「AはBではない」という裏返しの論理がはたらくことになる。「鈴木氏は大学教授だ」という文において、「鈴木氏」と「大学教授」には意味的差異がある。一方、「A=B」の条件を満たす「鈴木氏が鈴木氏だ」は意味を成さない。「A≠B」が有意味性の条件なのである。この意味的差異は、一方では、Aを語り尽くすことができないということを、他方では、その限界性故に、Aの言説の新たな可能性が絶えず開かれている、ということを同時に示している。
いずれにせよ、「AはBである」という表現形式を用いて用語の記述を行うわけだが、概念間の差異を示す定義だけでは、Aがどういうものであるかを示すことはできない、そこで、定義に加えて、用語の説明を行うことが必要となる。
定義が「Aとは何であるか」を規定する行為であるのに対して、説明は「Aはどういうものか」を明らかにする行為である。すなわち、定義は概念の差異化のために必要な行為であり、「何であるか」を明かせば、その役割は終わる。一方、説明は、「何であるか」ではなく、「どういうものであるのか」を明らかにするものであり、それを通して、用語(=概念)の意義が読者に了解される。
通例、定義というものは、それを厳密に行おうとすればそれだけ、わかりにくくなるものである。例えば、ある国語辞典では「リンゴ」を<バラ科の落葉高木、またはその果実>と定義されている。このままでは、かえってわかりにくくなる。そこで、説明がどうしても必要となるわけだが、説明の善し悪しは、読者が何を辞典に求めているかによって異なる。
説明は例示を主として行うが、説明は定義あっての説明であって、定義のない説明では、不十分である。例えば、「正義」の定義として、「『正義』とは公正な手続きを踏むことである」と記述したとしよう。このままでは、すっきりとは理解されない。そこで、それはどういうことかを説明するために、「二人の少年がいて、ケーキがある。母親は、ケーキの取り合いを避けるため、少年Aにケーキを切らせ、少年Bに選ばせるという手順を提案した」といった事例を挙げるかもしれない。しかし、例示だけ示され、「これが正義だ」と言われても、合点がいかない。定義上、公正な手続きとしての正義論が示されて、はじめて、説明が意味を成すのである。このように、定義のない説明は不十分である。
わかるための工夫
専門用語辞典では、捉えどころのないものに対して、定義と説明を通して、概念規定を行い、当該の用語が何であり、どういうものであるかを明らかにしなければならない。実際、定義だけでは、それがどういうものであるかを理解することは難しい。そこで、執筆者は、説明のしかたを工夫しなければならない。上述の通り、説明は例示によるものが中心となるが、比喩も例示の一形態である。
「たとえ」をうまく使った説明の例として、記号論における「関係的恣意性」という用語を取り上げてみよう。これは、定義上、「言語記号は、共時的な差異の体系であり、個々の項は他の項に依存しており、しかも、差異の体系としての関係的構造もなんら必然的な根拠を持ち得ない」ということを表す概念である。この定義は正確かもしれないが、一般の読者にとっては、おそらく何のことかよくわからないだろう。そこで、この概念がどういうものであるかを説明する必要がある。丸山圭三郎(1981)は「饅頭と風船」のたとえを使って、この用語の説明を試みている。
『箱の中に入っている饅頭と、同じ大きさの箱の中に押し込められている同じ数の風船をイメージしてみよう。その風船はただの風船ではなく、圧搾空気が入っていると仮定する。さて、饅頭の場合は、その中から1つ取り出して箱の外においても、当然そこには空隙が残されるだけで、箱の中の他の関係は変わらない。…… 圧搾空気をつめた風船の場合は、箱の中でしか、また他の風船との圧力関係においてしか、その大きさはない。もしその中の風船を1つ外に出すと、当然のことながらパンクして存在しなくなってしまう。また、残した穴もそのままではあるはずはなく、緊張関係におかれてひしめき合っていた他の風船が全部ふくれあがってたちまち空隙を埋めてしまう』(p.96)
これは難しい概念をわかりやすく、そして的確に説明するものである。饅頭の箱の場合は、項目の実体的同一性が前提となっているが、風船の箱の場合は、個々の項の実体性というものはもともと存在せず、あるのは隣接項との関係だけである、ということが示されている。さらに、風船の布置関係は共時的であり、なんら必然性は伴わないということが示されている。だから関係のあり方そのものが恣意的である、ということである。
新しいアイデアは、新しいコトバを必要とするが、それが何であるかが定義され説明されなければ、折角のアイデアも共有されない。教育についても同様である。コトバでコトバを説明する行為が教育活動の中心になるからである。
【参考文献】
丸山圭三郎:ソシュールの思想,岩波書店,東京(1981)