研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
第2回研究会レポート
欧州の言語能力アセスメント動向から考える日本の英語教育の今後
東京外国語大学 根岸雅史先生
ヨーロッパでは汎用的な枠組み(CEFR)のもと、外国語教育を進める動きが広がっています。さらに、言語能力を測るアセスメントについても、汎用的なものを開発しようとする動きが見られます。このような状況の中で、今回は、このCEFRや、CEFRをベースに開発されようとしている言語能力アセスメントの動き、さらにこれらによる日本の英語教育への今後の影響などについて、東京外国語大学の根岸雅史先生にお話しいただきました。
日本における言語能力アセスメントの現状
日本の言語能力アセスメントの状況について語る場合、いろいろな英語テストとか、学習指導要領などという視点から語ることもできると思いますが、ここでは文部科学省が打ち出した「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」1という視点から論じてみようと思います。これは、平成14年7月12日に出されたものですが、今年の3月で一区切りということらしいので、振り返るいい機会ではないでしょうか。
この中のキーワードは、「国民全体に求められる英語力」でした。中学卒業時までに英検3級程度、高校卒業時までに英検2級または準2級程度という目標2が、初めて設定されたわけです。
では、この目標の達成度は実際にはどうだったのでしょうか。実は、日本人の英語力の実態を知るのはとても厄介です。というのは、英検にしてもGTEC for STUDENTSやTOEICにしても、特定の受験者しか受けていないわけです。「教育課程実施状況調査」3はほぼ完全なランダム・サンプリングで行っていますが、調査目的が異なる上に、英検などとの関連づけはなされておらず、必ずしもみなさんにわかりやすい結果をもたらしてくれていません。ある県の中高生全員に英検の相当級がわかるテストを実施した結果によると、高校1年生の大多数が英検4級(中学2年修了程度)、高校2年生は準2級以上が20%以下で、戦略構想で掲げられた目標は達成されていませんでした。ただ、この県も特にレベルが低いわけではなく、むしろ、こういう調査をする中では比較的よいほうです。
今後、こうしたデータの収集とそれに基づいた目標設定がより必要になるのではと思います。その際に大事なことが2つあります。1つは、英語力の目標といった場合にいつも問題になっていたことですが、「夢」を語るのか、「最低保証」なのかを明確にして議論したほうがいいと思います。夢は語っていて楽しいですが、そうなると、みんな英検1級が目標になってしまいますから、現実をちゃんと見つめることが必要だと思います。夢を語りつつ一方で最低保証も定めるというように、ハイブリッド型の議論が必要である、という声もあります。もう1つは、達成目標を議論するときに、共通の尺度をもとに議論する必要があるということです。
世界各国の言語アセスメント
では、世界にはどのような言語能力を記述する枠組みがあるのでしょうか。ここでは、代表的なものを紹介します。まず、アメリカのACTFL(American Council on the Teaching of Foreign Languages)4 。ここで作っているガイドラインは、ヨーロッパの言語に限らず、広範な地域の多くの言語に適用できるように作られています。カナダにはCanadian Language Benchmarks5というものがあります。これにはいろいろな用途がありますが、移民の人たちの英語力の証明にも使われます。アメリカの学校教育の中での外国語学習のスタンダードを定めたのが、Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century6です。
ヨーロッパにはALTE(Association of Language Testers in Europe)7という組織があり、ここで作られたALTE Frameworkとかなり連動しているのが、今日これからメインでお話しするCEFR(Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment)8です。日本語では「ヨーロッパ言語共通参照枠組み」と訳されています。この開発は、Council of Europeによって1970年代に始まったプロジェクトに端を発し、その枠組みはあらゆるヨーロッパの言語で利用可能なように開発されています。
まず、レベルは大まかにABCの3つあり、下からBasic User、Independent User、Proficient Userから成っています。それがさらに2つずつに分けられ、A1からC2まで6段階あるわけです(下図参照9)。
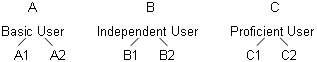
おそらくは、日本の高校生の多くはA1かA2あたりではないかと思います。具体的な技能についてですが、このCEFRでは大枠を3つに分けています。1つめが“Understanding”、これには“Listening”と“Reading”が含まれます。2つめが“Speaking”、そして3つめが“Writing”です。注目に値するのが“Speaking”を、やりとりを主とする“Spoken Interaction”と、発信を主とする“Spoken Production”との2つに分けていることです。
言語能力を記述するにはいろいろな記述の仕方があります。伝統的には文法や単語をどのぐらい知っているかということもあるでしょうし、一方で、日常的に「あの人すごくできるよ」とか「私って全然できないんですよ」というように言語能力を量的にイメージするときがあります。これは言語能力を単に量的に語っているだけですが、これに対して、CEFRは言語機能に基づいたCan-do statementsにより、その言語を使って具体的に何ができるかを表しています。例えば、“Writing”を例に取ると、一番下のA1レベルでは「新年のあいさつなど短い簡単なハガキが書ける」、B1レベルでは「自分の体験や印象をつづった手紙が書ける」、さらにC1レベルでは「自分自身を、ある観点から、一定の長さを持ち明瞭でわかりやすい構文で表現できる」などとなっています。
CEFRに関連したさまざまなアセスメントやリサーチ
このCEFRという枠組みができたことで、これをもとにさまざまなアセスメントが広まっていきました。大きく分けて、テストによるアセスメントとそうでないものの2種類があります。CEFRに関連したアセスメントの1つに、DIALANG10というものがあります。これはヨーロッパの14の言語についてインターネットで世界中から無料で受けられる診断テストです。日本人でしたら、指示文は英語を選ぶ人が多いと思いますが、英語やフランス語やドイツ語などのテストを無料で受けることができます。技能としては、リスニング、リーディング、ライティング、文法そして語彙の5分野です。CEFRは言語に依存しない枠組みであるのに対して、こちらは診断ですから、個別言語の能力の診断をしているところがおもしろいと思います。
もう1つ、CEFRに関連したアセスメントで、テストに代わるオルタナティブ(代替的)アセスメントと呼ばれているものの1つに、「ポートフォリオ」(European Language Portfolio)11というものがあります。ポートフォリオというと、カメラマンやモデルの人などの作品集というのが一般的と思いますが、自分の言語能力をいろいろな角度から書き出してみるノートのような形になっています。大人向けと子ども向け12がありますが、子ども向けのほうが記述はわかりやすくて意外にいいかもしれません。自分が今までにどんなふうに語学を勉強してきたかとか、今までに書いたものにどんなものがあるかとか、今どんなことができるか、などを書いていきます。こういうものが日本でも取り入れられるといいのではと思います。
最後に、CEFRに関連したリサーチもいくつか進んでいます。代表的なものにはCambridge ESOLで行われているEnglish Profileというものがあります。これはCEFRが言語に依存しない枠組みであることから、それぞれの言語で見たら各レベルの学習者の語彙や文法などはどうなっているのかを実証的に見ていきたいということで始められたものです。具体的には電子化された言語資料(コーパス)の巨大なデータベースを作って、学習者が発達とともにどういうふうに伸びているのかを見ようというプロジェクトです。おそらく、学習者の母語に関係なく普遍的に伸びていく要素と、母語に影響されて母語ごとに異なった発達をする要素とがあるのではないかと考えられています。とりあえずはライティングのサンプルから集めていくことになるようです。
CEFRはヨーロッパを飛び出して世界のスタンダードの1つになりつつあり、アジア諸国、例えば中国やタイなどでも採用され始めているような話も聞きます。日本でもCEFRに関する研究なども増えてきていることから、CEFRに関連したヨーロッパでの動きは、日本から遠い国での動きではなく、日本や東アジアの言語政策にも大きな影響を及ぼすかもしれない重要なファクターの1つであるといえるのではないでしょうか。
根岸雅史先生からのコメント
CEFRを日本の英語教育の枠組みとして利用しようとした場合、ほぼ利用可能であることはこれまでの研究からわかってきています。CEFRは汎言語の枠組みですが、これを英語の枠組みに限定して利用しようとした場合は、語彙や文法についての具体的な記述が可能となるでしょう。CEFRにおいてコミュニケーション・スタイルなどへの言及がほとんど無いのは、ヨーロッパという共通の文化基盤を持つ地域のための枠組みとしてCEFRが開発されたからでしょう。しかし、CEFRがヨーロッパを飛び出したときには、こうした視点がそれぞれの地域独自に付加される必要があるかもしれません。






