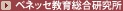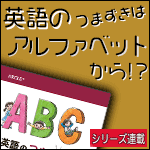研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
第2回 研究会レポート
詳細:「上智大学・ARCLE応用言語学シンポジウム2010:
英語の授業を変える‐発問で引き出す学習者とのインタラクション‐」
第1部 基調講演
「発問から広がる授業」
吉田 研作(上智大学)
「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」のその後
2002年に文部科学省は「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」というものを策定しました。その中で具体的な目標に、国民全体に求められる英語力として、例えば中学卒業時に英検3級程度、高校卒業時には準2級から2級程度の力をつけること、と明記されました。この中学卒業時に英検の3級程度、高校卒業時に準2級から2級程度という目標ですが、残念ながら現状を見ると必ずしも明るくはないと思います。特に高校のほうはなかなか厳しいところがあるのではないでしょうか。文部科学省の委員会等では、この戦略構想の策定から10年近くたった現状はどうなのか、今後それをさらに具体的に発展させていくためにはどうするべきなのか、が話し合われています。
我々のような大学に課せられている最も大きな課題としては、国際社会で活躍できる人材の育成が挙げられます。例えばTOEICでいえば730点ぐらいを目指してほしいということで、個別に見れば730点とれる学生はたくさんいますが、大学全体となるとほとんどの大学があてはまらないでしょう。そういう状況ですから、もっと具体的にどうすればよいのかを早急に考えていかなければなりません。
また、今回の学習指導要領の改訂では、いわゆる言語力の必要性がうたわれました。具体的に言うと、言葉を使って自分が考えていることをきちんと表現し、それを相手に伝えるということ、つまりはコミュニケーション力です。このコミュニケーション力を、国語だけではなくあらゆる教科を通してつけていかなければいけない、ということです。
外国語という観点で見てみますと、例えば小学校では、「コミュニケーション能力の素地を養う」とうたわれています。この「素地」が何なのかは議論があるところですが、ここでのポイントとは、単に英語を知識として学ぶのではなく、とにかく使えるようにするために、活動することによってコミュニケーション能力を育成しようというわけです。中学校では、4技能それぞれにおいて、実際に言葉を使うことを目標にしています。ここでも単に英語の知識を身につけるのではなく、本当に使える能力をつけてほしいということです。さらに高等学校では、4技能の統合的かつ総合的な力を身につけることと同時に、教師は原則、英語で授業をすることが示されました。教室以外に子どもたちが英語に触れる機会はほとんどないわけですから、せめて、英語の授業時間ぐらいは、教室を、英語を使う場面に変えようという発想だと思います。
コミュニケーション力が大事だということは、この10年間でやっと少し浸透してきたという感触があります。であれば、具体的にどのようにやっていくのかを考えるのが、次の大事なステップです。
日本の英語教育―Fish Bowl ModelとOpen Seas Model
私は10年ほど前から主に日本の英語教育について論じるときに、Fish Bowl Modelと、Open Seas Modelというたとえを使っています。まずFish Bowl Modelです。金魚鉢の中の魚は、世話をしてくれる人が餌をくれたり水を替えたりしてくれないと死んでしまいますね。世話をする人は、その魚が最良の環境で生きられるようにいろいろ手を尽くしますから、汚れがあってはいけないし、異物があってはいけない、餌もいいものをあげよう、と考えます。しかし、現実の世界というのはそんなにきれいな環境ではないわけですから、その魚は、基本的に非常に限られた、人工的な世界でしか生きていけません。
これと同じことが日本の英語教育、外国語教育にもあてはまります。今の中高生は先生がいなければ勉強ができない状況です。先生も入試のために、一番いい餌、完璧な英語の餌を一生懸命与えている状況だと思うのです。その際、自由に発言させるとエラーが多くなりますから、できるだけ限られた範囲で正確さを追求する授業を展開します。確かに入学試験や日本というEFLの環境の中で限られた範囲で英語を使うだけなら、それなりの意味があるかもしれませんが、世の中がどんどん国際化していく中で、Fish Bowlで満足していてはいけないだろうと思います。
これに対するのが、私がOpen Sea Model「大海モデル」と呼んでいるものです。大海原を自由に泳いで生きている魚というのは、自分で餌を探し、自分で住処を探し、力強く生きて行く。誰も世話してくれる人はいない。自然の中というのはきれいな環境ばかりではないし、餌だって完璧なものは少ないかもしれない。けれども、そこにあるものを食べなければ生きていけないわけで、そういう環境だからこそ力強い魚が育つのではないかと思います。
これを英語教育にあてはめると、大海の魚というのは自分から英語の餌を持ってきて、先生にその料理の仕方を教わりにくる生徒です。そこでの教師の役割というのは、ファシリテーターでありカウンセラーであると思います。例えば、京都のような観光地で、外国人観光客に話しかけて実際に英語を使ってみる。完璧ではないかもしれないが、そこで通じた、という喜びが味わえる。そういうことを通して、コミュニケーションの大事さ、正確さだけではなく、意志が通じる、意味がわかることが大事だという体験をしてもらいたい。つまり、私たち日本人にとって足りないのは、Open Sea Modelのほうであり、これがまだ十分にできていないのではないかと思います。
アクティビティはdisplay型からreferential型なものへ
もう1つ別の観点から言うと、アクティビティをdisplay とreferentialに分ける方法があります。例えば、先生が自分の腕時計を指して“OK, everybody, is this a watch?”と言ったら、生徒は“Yes, it is.”と答える。これも発問ですが、どれほどコミュニケーションの意味があるでしょう。なぜなら先生はこれが時計であることをわかっている。にもかかわらず質問するということは、生徒に意味がわかるかを聞くのではなく、答えるときの正しい言い方を確認したいだけなのです。しかし、同じYes/No questionでも、“Do you like cats?”と聞けば、形が知りたいのではなく、相手が本当に猫が好きかどうかを知りたい。これがdisplay とreferentialの大きな違いです。同じYes/Noの発問だとしても、“Do you like cats?”のほうはよりコミュニケーション、意味を伝えるための発問として使えるのです。
display型の発問でもう1つ例を出すと、“Is this a watch?”と聞かれれば、たいてい即座に“Yes, it is.”という答えが出ますが、“Dose the sun rise from the west?”という質問ではどうでしょう。おもしろいことに、これも答えは決まっているにもかかわらず、聞かれた人はだいたい3秒後ぐらいに答えます。何が違うかというと、考えなきゃいけない。考えるという作業もコミュニケーションにはものすごく大事です。ですから、すべてのdisplay型の発問が悪いわけではなくて、その使い方や種類が問題なのです。
中学、高校の授業を見ていると、短文が出てきて、それを訳すということがよく行われています。訳せば意味が理解できたと思い込んでいる人がいますが、実は文法が正しく使えたかどうかを試しただけで、前後と全然関係ない独立した文を訳しても、あまり意味はないと思います。前後の文や文脈によって、その文の意味というのは変わってくるわけですから。日本語でもよく例に出されますが、レストランで「私はうなぎ」と言えば、「私はうなぎを食べます」「うなぎをください」だけれど、例えば学芸会で「私はうなぎ」と言えば、「うなぎの役をやる」ということになる。Dwight Bolingerが言っているように、「言語というのは真空状態では存在しない」のであって、具体的なコンテクストに入って初めて意味を持ってくるわけです。
それに対して、referentialなものというのは、意味の交渉になっていきます。例えば相手が言ったことがわからなかったときに“What did you say?”や“Could you repeat that again?”などと、もう一度聞いてみる、“Do you mean this?”や“In other words, is this what you mean?”という形で確認をとるなど、あるいは逆に自分が言ったことが相手にわかったかどうか確かめたいときに使う“Do you understand what I say?” “See what I mean?”など。このような表現は、お互い意味がわかりあっているようなdisplay 的な状況では、意味はありません。こういう発問が意味をなすのは、相手と自分の間でまだわからないこと、未知の情報が存在するときであり、意味的に交渉しなければいけないものがあるときです。こういう意味のネゴシエーションがなければお互いコミュニケーションできないわけですから非常に大事になってきます。このような発問を入れるためには、よりreferential な活動をする必要があり、Open Seas 的な活動がより重要視されてきます。
具体的な例を見てみましょう。どこかの教科書に載っていた例文ですが、アメリカと日本の国旗が示されていて、国旗というのは戦時だけでなく、ワールドカップやオリンピックのときなど平和なときにもよく使われる、という説明のあとに次の文があります。The colors and design of a nation's flag stand for that country's land, its people and its history. Japan's “rising sun” flag, with its bright red sun on a white field, is one of the simplest flags in the world. America's flag, on the other hand, is quite complicated. It has thirteen colonies, and fifty white stars on a blue field, standing for the fifty states of America today.
これに対してよくある発問が、“What does a nation's flag represent?”といったものです。これは最初の文の “Colors and design of nation's flag stand for 〜.” が答えで、完全なdisplay です。そして、ここで終わってしまう先生が多いのではないでしょうか。このような内容についての設問が並んでいて、それが終わったら「これで解釈終わり」。これで生徒たちの英語を使う経験を増やそうというのは、とても無理だと思うのです。
もう1つよくあるのはTrue or Falseです。“America's flag is considered to be one of the simplest in the world”、これは当然Falseですが、「はい、そうですね、では次に行こう」となる場合が多いのではないでしょうか。では、どこで生徒が自分の意見を言うのでしょう。要するに授業の中で、displayな問いというのが非常に目立ち、本当にreferential な活動や、Open Seas 的なものというのはあまり見られないのです。最後にいきなり、“What do you think about the American flag?” と聞かれても、「どう思うって言われても…」と思いませんか。あるいは、「じゃあ、2人でディスカッションしなさい」と言われても、何をディスカッションすればよいのでしょうか。何らかの形で生徒たちに英語を使わせたい、コミュニケーションさせたいという意図はわかりますが、これでは無理があるように思います。
相手の発言を繰り返す―full repetition とpartial repetition
次に紹介したいのは、発問ではなく相手にしゃべらせるための方法です。これは相手が言ったことを繰り返すもので、例えば“I went to Disneyland yesterday.”であれば、“Oh, you went to Disneyland yesterday!”がfull repetition、“Oh, Disneyland!”ならpartial repetitionです。相手に対して自分は聞いていますよ、というシグナルを送っているわけです。それからもう1つ、commentingというのがあります。先ほどの“I went to Disneyland yesterday.”であれば、“Oh, really?”や、“Oh, that's interesting!”などとコメントをするというものです。
それでは会場の皆さん、ペアになって次の4つの方法(1)Yes/No question、(2)W/H question、(3)full repetition, partial repetition、(4)commenting(相手の発話にコメントする)、それぞれだけで会話してみてください。(会場の参加者による実践)どうでしたか。最初のYes/No questionでは、話が弾まないことがわかったのではと思います。それからW/H questionは会話というよりインタビューになってしまう。3番目のfull repetition、partial repetition、これは比較的楽だったかもしれません。でもこれはやりすぎると相手を不快にさせるので注意が必要です。では最後のcommentingが一番話しやすかったという方が多かったのではないでしょうか。つまり発問とは、質問するだけと思われるかもしれませんが、実はそうではなく、相手から情報を引き出し、自分も情報を与えるということで、コミュニケーションとはこのやり取りなのです。
相手の知らない情報を足す―plus one dialogueとstrategic dialogue
以前流行したものにplus one dialogueというのがありました。これは、簡単なダイアログの最後に、どちらか1人に相手の知らない情報を足して言ってもらうことで、少しはreferentialなものにしようという意図があります。例えば、
Jim: Hi, Bill.
Bill: Hi, Jim. Thanks for inviting me over today.
Jim: Oh, I'm glad you could make it! Come on in and make yourself at home.
Bill: Thanks.
というダイアログに、Billの最後に“Excuse me, Jim, can I use your bathroom?”というのを付け加えてもらいます。Jim役はそれを知りません。いろいろな研修会などでやってみたのですが、Jim役のほうは、“Oh, sure. Over there.” とか“Go ahead, use it.” などと返答します。それで終わってしまいますが、それでも一応新しい情報はあり、少し会話を発展させることが可能です。
しかし、ここからもう一歩先に進めます。これはstrategic dialogueと私が命名しているものですが、先ほどの会話にさらに加えて、Jimのほうにも「トイレが故障している」という、Billの知らない情報を与えておきます。そこでもう1回会話する。そうすると、Billが「トイレを使わせてもらえますか」と言ったところで、Jimは“Oh, I'm sorry, our toilet is out of order right now.” さあBillは何と言うでしょう。これを入れるだけで、色々な発言が生まれて、会話が発展していくのです。
これが先ほどと違うのは、problem solvingが加わっている点です。plus one dialogue だけだとあっという間に終わってしまいますが、problem solvingをするとなると、そこから会話が弾むのです。思考しながら一生懸命自分でその問題を解決しようとしていく。だからこれも発問ではありますが、発問から発展して、さらにどのように会話を広げていくかということが大事です。
もう1つ、日本語を使うという方法もあります。例えばディスカッション。グループに分けて「はい、やって」と言った途端に、発問どころか誰も何も言わなくなってしまう。であれば、まずディスカッションは日本語でやってもいいと思います。出てきた結果を、みんなでどう英語に置き換えたらいいかを考える。日本語でも、コミュニケーションというのは内容が大事で、外国語自体の能力が低いために内容まで踏み込めない場合は母語をうまく利用することで、そこで考えたことを今度は外国語にしていくというのでもよいと思います。このような活動を通じて、発言量を増やすことも多少は可能であろうと思います。
生徒たちが英語を使う場面にどれだけ多く触れることができるか
最後に、発問から発信につなげるためには、生徒たちが英語を使う場面にどれだけ触れることができるか、その場面をどれだけ与えられるかというのも大きなポイントです。これはGTEC for STUDENTSを使ってSELHi校、非SELHi校に対して行った調査結果でも明らかです。1年生ではほぼ同じ結果だったのが、2年、3年と学年が上がるにつれてどんどん差が開いていく。つまりそれだけコミュニケーションの実践、つまり、英語に触れる機会をたくさん設けることが、大学受験でも優位に働いているわけです。ですから、コミュニケーションを多くするということが決して受験にマイナスには働いていないのです。また、別の調査で、同じくGTEC for STUDENTSを用いて、SELHi校、非SELHi校、ポストSELHi校に対して行った調査では、ポストSELHi校のスコアが一番高かった。これは非常に興味深い結果で、3年間SELHi校として英語に取り組んだ経験を生かし、それ以降ももっと英語力を伸ばす可能性があるということです。このような点から、発問、発信、さらにこれらを発展させたコミュニケーションはますます大事になると思います。