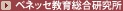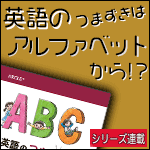研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
2012年度 第3回 研究会レポート
ARCLE研究会 「英語教育研究 次年度新課程を迎える高校英語、『授業は英語で』どのように行うのか。」
2012年9月30日に今年度3回目のARCLE研究会を開催しました。今年のARCLEは次年度より新課程を迎える高校英語をテーマに活動しています(12月にシンポジウムを開催いたします)。今回の研究会では、12月のシンポジウムで実践事例をご紹介いただく群馬県教育委員会 津久井貴之指導主事(2011年度パーマー賞受賞)をお迎えし、津久井先生の実践DVDを拝見しながら、新課程が本来的に目指す英語の指導はどのようなものかを議論しました。ここでは、その議論を踏まえた所感をご紹介します。
「授業は英語で」−忘れられた「言語活動」
東京外国語大学 根岸雅史
高等学校新学習指導要領の英語の「授業は英語で行うことを基本とする」という言葉が注目を浴びている。しかし、本当に注目すべきは、解説にある「英語による言語活動を行うことが授業の中心となって」いるという部分だろう。つまり、「言語活動」なしに、教師が一人で英語で話していてもだめだということである。
また、津久井先生の「単元や授業のねらいを明確にすること≠その授業で身につけること」という指摘は、まさに的を射ている。高校生が使う表現が中1、2レベルというのはよくあること。授業のねらいを明確にして、それを直後に評価する。しかし、それでできていたからといって、生徒が本当に授業のねらいを身につけることになるとは限らない。これは今後の英語の評価のあり方への重要な問題提起となっている。
「英語で授業」が可能にする「教科としての英語」から「言葉としての英語」へのシフト
慶應義塾大学 田中茂範
多くの生徒は「英語」というものを「教科」として捉える傾向がある。彼らにとって、英語は教科書の中にあり、問題集の中にあり、そして英文和訳の中にある。しかし、本来の英語は生活の中に息づく「言葉」のはずである。
高等学校新学習指導要領における「コミュニケーション英語」は「言葉としての英語」観に強調点を置くものである。だとすれば、新しい教科書を導入するだけでなく、その教え方も新たにする必要がある。新たな指導法の開拓において新学習指導要領の中にある「英語の授業は英語で行うことを基本とする」の文言は十分にインパクトのあるメッセージを含んでいる。
英語で授業をすれば、「英文和訳」という言語の置き換え活動を抑制する効果がある。英語で授業をしているとき、「この英語を日本語にしよう」というのは端的に不自然だからである。ここで注目したいのは「英文和訳」は従来の日本の英語教育の象徴的な活動であったということである。教師も生徒も和訳を通して英文を理解することに拘泥してきた。しかし、英語で授業をすることで、「英文和訳」活動が封印されると、新たな活動(英語の学び)の地平が拓ける可能性が出てくる。そして、その新たな活動を通して、生徒の英語観も「教科としての英語」から「言葉としての英語」にシフトしていくということが期待できる。
おそらく、さまざまな言語活動が工夫されるだろう。しかし、「言葉としての英語」という観点からみて健全な活動は、「authenticで、meaningfulで、personal なもの」であるはずである。しらけない場を作り、授業が生産的で創造的な活動になるためには、教材も活動も本物であること(authenticであること)を追求する必要がある。しかし、同時にauthentic であることが生徒に響く効果を生むには、提示される教材と活動は meaningful でなければならない。理解できる(わかる)ということが authentic であることの条件なのである。そして、それに加えて、personal であること、これが「言葉としての英語」に実感(reality)を与えるための条件である。
いずれにせよ、生徒一人ひとりが我がこととして英語を引き受け、英語を我がもの(my English)として構築するという自覚を持つことができるような教材と活動が必要となる。
教科書をベースとしたcan-doを考える
東京外国語大学 長沼君主
学校の文脈に合わせたcan-doリストを作成する際に、最終的に期待されるパフォーマンスを記述するのではなく、教科書をベースとした日頃の学習のプロセスを記述することで、どのような学びが起きているかが可視化される。現在、小中高それぞれの教材・教科書でcan-do作成に取り組み始めているが、留意すべき点は異なる。
小学校外国語活動では、定着を前提としない活動づくりにより、毎回の学びを保証するための仕掛けづくりと、毎回の授業および各課を通じた児童の変容を引き起こし、「できる感」を与えるための活動の段階化が求められる。中学校の教科書では、文法中心の活動の組み立ての中で、背後に潜む機能に焦点を当て文脈化を図ることに加え、本文における文法への気づきを高める工夫が必要となる。
高校の教科書では、本文、ドリル、活動を有機的に結びつけ、英語での発問を通して本文の深い読みを促すと同時に生徒の発話を引き出し、さらには、内容的理解をベースとした活動をデザインすることで、内容言語統合型(CLIL)の思考を求める学びにつなげていくことができる。
こうした教科書の特徴をとらえながら、一貫した学びをどう展開していくかが今後の課題となるであろう。
CAN-DOを目指す英語教育のあり方
上智大学 吉田研作
CAN-DOを具体的な達成目標に置くことで、英語教育の改善を図ることが、現在文部科学省が考えていることだが、今回の議論の中でも出てきたように、気をつけなければならないことは、教師がCAN-DOの目標に向けて一生懸命教えても、生徒が実際"Yes, I can."と自信を持って言えるようにならなければ意味がない、ということである。つまり、CAN-DOを目標化しても、教師が「この単元では○○というCAN-DOを教えるんだ」と意気込んで、dialogueの暗記、CAN-DOを実現するための表現のドリル、あるいは、パターン練習のような、いわゆる教師中心の授業を展開したとしたら、結局空回りしてしまうだろう。本当にCAN-DOを目標にするためには、生徒中心の授業展開の中で、いかにコミュニケーションをさせる機会を増やすかがポイントだということを忘れてはならない。