研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
第2回研究会レポート
CEFRがヨーロッパに与えたインパクトと日本の英語教育への示唆
東京外国語大学 根岸雅史
ヨーロッパでは汎用的な枠組みであるCEFR(Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment)のもと、外国語教育が行われ、さまざまな方面に影響をもたらすとともに、その内容や活用について多様な意見も出てきています。今回はヨーロッパのCEFRに関する動き、関連した調査および英語学習に関するプロジェクトなどの一部をご紹介します。
CEFRとヨーロッパに与えたその影響
CEFR1とは正式にはCommon European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessmentという名称で、日本語では「ヨーロッパ言語共通参照枠組み」と訳されています。これは、1970年代に始まったCouncil of Europe2によるプロジェクトに端を発し、その枠組みはあらゆるヨーロッパの言語で利用可能なように開発されています。
具体的にはレベルはABCの3つあり、下からBasic User(A)、 Independent User(B)、 Proficient User(C)となっています。それがさらに2つずつに分かれ、A1、A2、B1、B2、C1、C2の合計6段階になっているわけです(下図参照)3。
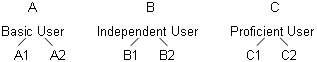
CEFRは言語機能に基づいた‘Can Do’statementsにより、その言語を使って「具体的に何ができるか」を明記しています。例えばWritingでいうと、一番下のA1レベルでは「新年のあいさつなど短い簡単なハガキが書ける」、B1レベルでは「自分の体験や印象をつづった手紙が書ける」、さらにその上のC1レベルでは「自分自身をある観点から、一定の長さを持ち明瞭でわかりやすい構文で表現できる」などとなっています。
このCEFRが具体的にどのようなところに影響を与えているかというと、まずは「外国語教育政策」の部分で、例えば、シラバスやカリキュラム、テスト、教科書などです。しかし、「教員養成」や「教室」への影響という部分になると限定的で、影響が少ないと言われています。ただ注意しなくてはいけないのは、ヨーロッパの外国語教育は日本に比べ、そもそもCEFR的であるということがあります。その点で、「影響が少ない」というレベルが日本の「少ない」とは異なることに留意しなければいけません。
CEFRについての批判も出てきています。例えばDaniel Costeは、「‘Can Do’statementsを記した6段階の表ばかりをクローズアップして議論されており、CEFR自体のコンセプトや、使い方などがほとんど無視されている」というような批判をしています。またGlenn Fulcherは、CEFRに対して「教員の判断をもとに作成されたものであり、第二言語習得の理論からすると、かなりおおざっぱであり論理的ではない」と批判しています。もう1つ、最近ではCEFRがかなり大きな影響力を持つようになってきたため、権威的に使われるようになってしまっているという批判もあります(“CEFR police”と言われています)。本来の使用目的は、「参照枠としてこれをもとに使ってください」というものだったのが、「きちんと使っていない」などと非難されてしまうことがあるのです。
※CEFRについての詳細は以下の「2008年度第2回研究会レポート 欧州の言語能力アセスメント動向から考える日本の英語教育の今後」をご参照下さい。
https://www.arcle.jp/report/2008/0002.html
ヨーロッパ各国の外国語教育の成果を測る試み
次に、言語能力の調査について紹介します。ヨーロッパ各国の外国語教育の達成度をみるという目的で、The European Survey on Language Competencesというものが2011年に実施される予定になっています。開発・実施主体は、ヨーロッパ各国の大学など8つの組織で作られたSurveyLang4というところです。注意しなければならないのは、日本でも全国学力テストを実施すると、どこの県が1位、どこの県が最下位などと報道されたように、どんな公表の仕方をしたとしても必ず、どこが1位、どこが2位というふうに出てしまう可能性があるということです。それは本来の趣旨ではありません。
この調査は、“Lisbon Strategy”という戦略に端を発しています。それによると、ヨーロッパは2010年までに“the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world”を目指すという文言があります(Council of the European Union, 2000, p. 1)5。
このknowledge-basedというところがかなり重要ではないかとみています。つまり、言語学習、言語教育というところが強調されたということです。さらに、小学校ぐらいから、少なくとも2言語を教えるということをヨーロッパは目指しているわけです(Jones & Saville, 2009, pp. 52-53)6。
さて、この調査の内容を具体的に言いますと、ヨーロッパ全体でsecondary education(中等教育)の外国語教育の成果や達成度をCEFRの6段階のレベルでみていこうというものです。もし日本で実施するならば、中学3年生時点での達成度をみることになります。調査としては2つのデータから成り立っていて、1つが言語のテスト(フランス語、ドイツ語、英語、イタリア語、スペイン語など)、もう1つがアンケートですね。対象は生徒、教師、校長となります。ですからこれは単純にテストではなく、どういう状況での外国語教育で、どんな結果がみられるかを調べる、ということを盛んに強調しています。
目的としては、「政策立案者、教師、そして学習者の三者に、情報を提供すること」と書かれていますが、もともとは外国語教育政策をどうするかという目的のために実施するものですから、おそらく政策立案者に対する情報提供が主になるでしょう。具体的なテストの内容については公表されておらず、我々には何も伝わってきていません。スピーキングテストが除外されたということ、リスニングとリーディングはパソコンを使用して行うということだけはわかっています。ライティングは実際に書かせるということですが、それ以上のことはわかりません。
そして、ここからがポイントなのですが、学習者をCEFRの6段階のうちA1からB2までの4段階にあてはめて、どこに位置するかを判断するそうです。上の段階のC1、C2レベルについては考えないとされています。secondary educationの成果をわずか4つの段階で区別しようというのですから、アバウトな話とも言えます。
ヨーロッパ各国の国の大きさや外国語教育事情もさまざまです。たとえば、オランダやベルギーでは国が小さいので外国語教育にはかなり力を入れていますが、ドイツやフランスあたりはやはり大国ですし、それほど力を入れてはいないという現状があります。フランス大使館の人から聞いたのですが、フランスは、実は英語教育についてはかなり危機感を持っているということがわかりました。フランスでは英語科目の位置づけがかなり低い。日本だと3教科というと国語、数学、英語だと思いますが、フランスでのそれは圧倒的にフランス語と数学、それに続いて理科、社会、さらに下がって芸術があり、外国語というとそれより低い位置づけなのだそうです。これはちょっとショックでしたね。当然、教師の位置づけもそのような順番になってしまい、授業時間も楽しく過ごせればいいという程度のものになってしまう。ですから、ヨーロッパでの外国語教育の成果については、それぞれの国の事情がかなり違うので、単純にどこが1位とは言えないと思います。
学習者の英語習得プロセスについての調査
これからお話しするEnglish Profile7略してEPは、これまでお話ししたCEFRやそれに絡む調査とは少し別の話です。EPを簡単に説明すると、「世界における英語の学習・指導・評価の向上を目指して作られた、長期間にわたる学際的共同プログラム」となります。世界の研究者・教師・教育行政に関わる人々と共同して、英語学習者がCEFRのレベルをどのように辿っていくのかを調べています。
繰り返しになりますが、CEFRというのは、ヨーロッパ全体に共通の参照枠組みとして作られています。ヨーロッパにはさまざまな言語があるわけですが、それを共通の枠組みにはめるということは、結局、個別の言語に関する記述、例えばこの言語のこの文法事項はこのレベルである、というようなことは書かれていないということです。そうなると当然、枠組みは共通だけれど、教えるのは個別の言語なのだから、それぞれの言語でのレベルはどうなるのかという話になってきます。
この類の研究としては、ドイツ語に関してはProfile Deutsch8というプロジェクトがあります。英語の場合は、CEFRのもととなったThreshold9やWaystage10などの文献がもともとあったわけです。しかし、これらは専門家たちによって書かれたもので、学習者の実際の言語データに基づいて作られたわけではないため、実証的なデータに基づいたEnglish Profileを作っていこうというのが、EPによるプロジェクトの狙いだと思います。
現在、EPには3つのプロジェクトがあります。まず、学習者がそれぞれのレベルで実際に産出する言語を調査するためのプロジェクトがあります。今、世界中から参加者を募っているところで、東京外国語大学も参加しています。このプロジェクトでは、CEFRの6段階のレベルを特徴づけ、区別するcriterial features(基準特性)をみつけようとしています。つまり、A1の特性、A2の特性は何か、A2になるとA1とどこが違ってくるのかを、これまでは直感で判断していたのですが、コーパスを用いた調査による実証的なデータに基づいて探していこうというわけです。また、世界中に参加を募っているという理由は、外国語学習における母語の影響がどれだけあるかということを調べるためです。
2番目に、B2やC2といった上位レベル向けに焦点を置いて、カリキュラムと教材を研究するというプロジェクトがあります。これはUniversity of Bedfordshire Centre for Research in English Language Learning and Assessment (CRELLA)11で、Cyril Weir教授を中心として行われているものです。3番目のプロジェクトは、アセスメントが調査の柱になっています。これは学習者の言語知識および言語使用という観点から、言語スキルがどう発達するかに焦点を置いています。
EPの現状ですが、東京外国語大学も参加してプロジェクトを進めています。データ収集の方法がほぼ固まり、これから開始するといった状況です。今後、日本では高校や中学にも調査に参加していただければと、可能性を探っているところです。これらの状況を日本の英語教育への影響という視点からみてみると、日本でもCEFRに関する研究は増えてきていると言えるのではないでしょうか。今後CEFRが世界のスタンダードになっていくのか、その動向を注意深くみていく必要があるように思います。
根岸雅史先生からのコメント
この枠組みを日本に初めて紹介した当時、「日本人の英語学習者の目標としては、Bあたりではないか」という発言を私がしたところ、「C2を目指さずにどうする」というような発言をされた方もいました。ただ、これまでの色々なデータをみていると、日本人英語学習者の多くはAレベルで、かなりよくできる人たちでもせいぜいB2レベルではないかと思うようになりました。もしこの推測がある程度当たっているとすると、日本人英語学習者の発達段階を細かく記述する枠組みとしては、かなりおおざっぱであると言えるかもしれません(なにしろ、日本人のほとんどをA1かA2のレベルのどちらかに入れ込もうというのですから)。しかし、国家戦略として「日本はどの程度の英語力の学習者をどのくらい育成するか」という点について世界共通の枠組みで議論するためには、非常に有益な枠組みと言えるのではないでしょうか。
| 1 | http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf |
| 2 | http://www.coe.int/DefaultEN.asp |
| 3 | http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf, p.24 |
| 4 | http://www.surveylang.org/ |
| 5 | Council of the European Union. (2000). Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions, p. 2. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm |
| 6 | Jones, N., & Saville. N. (2009). European Language Policy: Assessment, Learning, and the CEFR. Annual Review of Applied Linguistics 29, pp.52-53. |
| 7 | http://www.englishprofile.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44 |
| 8 | Glaboniat, Manuela.(2005). Profile Deutsch. Berlin: Langenscheidt. |
| 9 | Ek, J.A. Van & Trim, J.L.M. (1991) Threshold Level 1990. Cambridge, Cambridge University Press. |
| 10 | Ek, J.A. Van & Trim, J.L.M. (1991) Waystage 1990. Cambridge, Cambridge University Press. |
| 11 | http://www.beds.ac.uk/research/bmri/crella |






