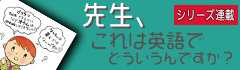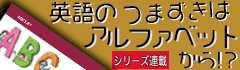研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
【連載】先生、これは英語でどういうんですか?
−生徒が間違えやすいことを、本質的な意味から考え、指導に生かす
>>その他の記事はこちら
The sun rises [ ] the east and sets [ ] the west.
そこで、ARCLEより2013年度新企画として、英語の語彙や文法について深く本質的な知見をお持ちのARCLE研究理事、田中茂範先生(慶應義塾大学)によるコラム、『【連載】先生、これは英語でどういうんですか?』をお届けします。
第1回目は理論編として「英語学習における日本語の影響(L1フィルター)」です。2回目以降は、指導実践に役立つ事例を具体的に多数お伝えしていきます。
第1回 英語学習における日本語の影響(L1フィルター)
慶應義塾大学 田中茂範
人は既に知っていること(既知)を利用して新たなこと(未知)を学びます。これは学習理論の第一原理だといえます。だとすると、日本人学習者が英語を学ぶ際には、日本語を利用するのは自然なことですし、それは不可避なことです。英語の学習は一種の情報処理であり、その処理には既知の第一言語(=日本語)が影響します。第一言語(L1)である日本語のフィルターを通して第二言語(L2)である英語を学ぶということです。以下では、この第一言語の影響のことを「L1フィルター」と呼ぶことにします。
インプットとしてn個の英語が与えられた場合、そのすべてを一様に学習するわけではありません。ある項目は学習されやすく、ある項目は学習されにくいということが起こります。この「選択学習」にL1フィルターが作用します。例えば、on の用例で a cat on the bed と a ring on her finger の2つが示された場合、a cat on the bed のほうが学習されやすいことが予測できます。それは日本語の場合と発想が似ており、処理がしやすいからです。
また、情報処理には「取り込み(intake)」の部分だけでなく、取り込んだ項目を知識としてどう捉えるかという「表象(representation)」の側面があります。ここでもL1フィルターが作用します。例えば a cat on the bed だと「ベッド(の上)の猫」、a ring on her finger だと「指にはめた指輪」として理解し、学習者は「on には『指にはめる』という意味もあるのか」と考えてしまうかもしれません。
L1フィルターの影響は、英語を使ったり、理解したりするという「運用のレベル」でも作用します。例えば、「太陽の昇り沈み」を表現するのに英語では The sun rises in the east and sets in the west. と表現します。しかし、日本人学習者はL1フィルターを通して「太陽は東から登って、西に沈む」として理解する可能性があります。そして、英語を使う際にも、The sun rises from the east and sets to the west. と表現するかもしれません。これはL1フィルターによる誤用です。
このようにL1フィルターは、選択学習、表象(理解)、運用の局面で作用します。これは自然なことですが、日本語を媒介として英語を学ぶことから有効な英語学習が阻害される可能性があります。そこで、次回からは「どうすればよいか」について考えていきます。
【その他の人気コラム】