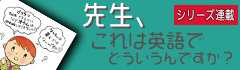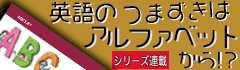研究ノート・研究会レポート一覧
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
【新連載】小学校英語で行うリーディングの基礎指導とは
≫その他の記事はこちら
第5回 書き言語と音声言語
青山学院大学 アレン玉井 光江
今までこのコラムでは初期のリタラシー指導で必要なことについてシリーズで書いてきました。今回はこのコラムの最後としてリタラシー指導の際に重要な音声言語の発達について考えてみたいと思います。
1.母語でのリタラシーと音声言語の関係
母語獲得の過程を見ると、「書き言葉」を身につけるためには「話し言葉」が十分に発達していなければいけないことがわかります。音声言語がリタラシーの土台になると考える研究者は多く(Snow, Burns, & Griffin, 1998、Roskos, Tabors, & Lenhart, 2009)は、特に就学前に獲得する音声言語が後のリタラシーおよび学習の成功に大きく影響すると考えています。
2.第二言語におけるリタラシーと音声言語
子どもに限らず、第二言語学習者がリタラシーを獲得するときの大きな壁は、「書き言葉」の土台となる「話し言葉」が十分に発達していないことです。私たちは英語の音声言語が十分に発達していない状態で英語の読み書きに挑戦しています。しかし、私は外国語教育においても音声言語を育てることがリタラシー指導に必要であると思っています。例えば、フォニックス指導で得た力で、書かれている単語を音声化できても、単語(の音)を知っていなければ理解できません。特に初期段階においては、音声で英語を理解している力が読解力に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
それでは、これらの音声言語はどのような状況で獲得できるのでしょうか? 私たちはこのような音声言語力を仲間や周りの大人たちとの自然なやり取りの中で、意味のある文脈を通して身につけてきたと考えられます。子どもたちが興味を抱くのは意味(meaning)の世界であり、形式(form)の世界ではありません。言語習得という観点からすると、教室は不自然な環境ですが、子どもたちがなるべく自然に、意味のある文脈の中で英語に触れることができるように工夫することが重要です。わかりやすくするために1文レベルや単語レベルでの言葉ばかりを提供していると、そこには生きた文脈は存在せず、本当の意味での言語習得は望めないでしょう。また簡単なダイアローグのやり取りでは、子どもはどのような文脈のもとで言語が使用されているのか想像するのが難しく、必然的な言葉のやり取りを学習することも難しいでしょう。
以上のような理由から私はストーリーテリングや絵本を利用して、子どもたちが想像力を働かせながらなるべく自然な音声言語に接することができるように指導しています。ストーリー性を持った伝統的な歌やチャンツ、また絵本の読み聞かせやストーリーテリングなどを積極的に取り入れられることをお勧めします。
参考文献
Roskos, K. A., Tabors, P. T., & Lenhart, L A. 2009. Oral Language and Early Literacy in Preschool: Talking, Reading, and Writing. International Reading Association.
Snow, C. E., Burns, M. S. & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young Children, National Academy of Sciences-National Research Council
【連載】小学校英語で行うリーディングの基礎指導とは 一覧
【連載】英語のつまずきは、アルファベットから!? 〜大人が気がつきにくい落とし穴〜 一覧
公立小学校における外国語について―移行期1年目に思うこと―